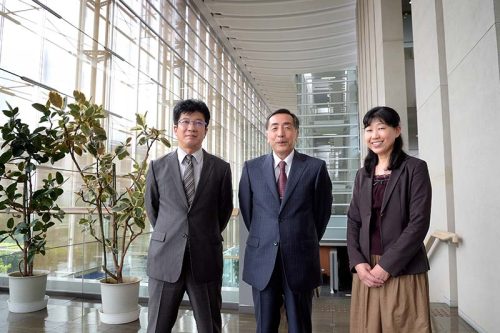MAGAZINE
データ利活用はコミュニティのレイヤー毎に考えるべき
続いて、森さんの「データのプライバシー問題などで、うまく行った例とうまく行かなかった例を教えて欲しい」という質問に対し、小島さんはうまく行かなかった例として、昨年まで在籍していたスタンフォード大学時代に携わった、アメリカの研修医を全国に配置する研究について話しました。
この研究では実データをもらう段階になった時に、プライバシーの問題だから出せないという事態が生じました。たまたま共同研究者が研修医のマッチを行っている人と知り合いだったため入手できたそうですが、そういうデータは個人的なつながりや信用がないと、なかなか入手できないという問題があるそうです。
日本ではデータ利活用がなかなか進まないという問題をよく聞きますが、これは日本だけの特殊事情ではなく、アメリカや他の国でも昔は全然データを取れなかった、今もまだ難しいというのが現状だと小島さんは話します。データの活用や研究知見を実装していくということに関しては、アメリカでは1990年代から2000年代くらいにかなり大変な思いをして挑戦した人たちがいて、日本ではまだそういう例が足りないのが現状だと小島さんは指摘します。
マッチングの問題やその制度設計においてはアメリカが進んでいると言います。その成功例として小島さんが挙げたのが携帯電話に使う電波周波数帯域のオークションの事例です。アメリカでは1990年代の中頃に始まり、最初は導入に非常に苦労したそうですが、いまではOECD加盟国の日本以外のすべての加盟国で行われています。
データ利活用が進んでいる国の例として、小島さんはスカンジナビア諸国を挙げました。そして、「制度設計の面ではまだ日本はほとんど進んでいない。しかし、帰国前には不安だったけれどもかなりたくさんの問い合わせが企業からあり、一気に進むのではないかという希望を持っている」と答えました。

森さんは次に落合さんに対して、今後データは個人情報として保護されるべきなのか、それとも国や企業が活用できる状態が進むべきなのかを尋ねました。
落合さんは、「個人情報としてデータは間違いなく保護されるべきだ」という立ち位置を明確にした上で、適正な環境をデザインする上では、どのコミュニティにおいてどう利活用を進めるかというレイヤーを、一個一個考えていく事が大切だと答えました。
「小さな自治体であるならば、そこに参加している人たちの意思の総合でやっていくことはあると思います。企業のサービスの上で自分のデータがどう活用されるかについては、個人がその企業に対してどういうデータを提供したいかという問題だと思います。国の場合は、個人情報に対する考え方はある程度センシティブでなければならないなと思っています」

DATA
登壇者名 落合 陽一 プロフィール ピクシーダストテクノロジーズCEO / 筑波大学准教授/筑波大学デジタルネイチャー開発研究センター センター長
筑波大学情報学群情報メディア創成学類、東京大学大学院学際情報学府博士課程修了。
筑波大学学長補佐・准教授・デジタルネイチャー推進戦略研究基盤長、大阪芸術大学客員教授、デジタルハリウッド大学客員教授を兼務。
次世代のコンピュータ技術を開発するピクシーダストテクノロジーズ株式会社のCEOも務める。登壇者名 小島 武仁 プロフィール 経済学者/東京大学大学院経済学研究科教授、マーケットデザインセンター・センター長
東京大学を卒業後、ハーバード、イェール、スタンフォードと最高学府に在籍。2012年に米スタンフォード大学でテニュア(終身在職権)獲得。東京大学に新設された「東京大学マーケットデザインセンター(UTMD)」センター長に就任。人と人、人とモノの最適な組み合わせを考える「マッチング理論」を研究している。