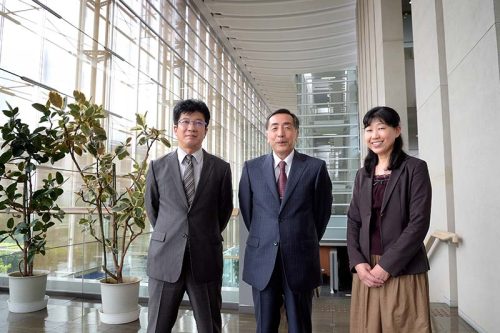MAGAZINE
CROSS TALK 6
FUSION of individuality 未来を変える個性の育み方と、描く次の社会。
もう一歩深く考えるきっかけを与える作品を作っている
長谷川さんは、スペキュラティブデザインという手法を用い、テクノロジーと人が関わる問題にコンセプトを置いた作品を作っています。
テクノロジーによって今までできなかった事ができるようになる。そこに希望を持っていると長谷川さんは語ります。
例えば、同性間で子どもを持つことが可能になるかもしれません。それを可能にする技術ができた時に、どういう未来が見えるかを示し、マイノリティーの人々に対する技術について議論をするための装置として作ったのが「(IM)POSSIBLE BABY, CASE 01: ASAKO & MORIGA」という作品だと長谷川さんは説明します。

この作品は実際に結婚していたレズビアンカップルの遺伝情報をシェアしてもらい、そこからどういう性格か、どういう食べ物が好きかを推測し、どういう朝食があり得るかを何気ない家族団らんのイメージとして表現したものです。長谷川さんは、このような作品を提示することで、人々が今まで気付かなかった問題を視覚化し、議論を深めようとしています。

「(遺伝子)技術を基に『こういう家族があり得るかもしれないですが、これについてどう思いますか』と尋ねると、大抵は『その技術ダメでしょ』という反応が返ってきます。そういうところで反射的に止まっている思考を、いろんなヒントを与えてあげる事で、もう一歩深く考えてみる事を促す作品を作っています」
子どもたちにはもっとリアルな経験が必要
二人の自己紹介の後、司会の森さんは中邑さんに「受験中心の学びは知識量を増やす一方で、知識を活用して課題を解決する力が低下しているのではないかと言われてきた。現在の一般的な学校教育をどのように見ていますか」と質問しました。
中邑さんは、「今の教育に乗っていけば親は何も考えなくていい。けれども、子どもにそれが合っているか、誰も考えていない」と答えます。
「みんなこう生きるべきだと子どもに押し付ける。その結果、特性が合わない子はそこで苦しむ。読み書きはみんな生まれつきできると思ったらそうではなく、読みが苦手な子、書きが苦手な子はいる。特に書きが苦手な子は、今の受験制度から間違いなくドロップアウトする。そういう子は評価されないし、自信を無くしていく」

もっと個々の特性に応じた自由な学びを与えないと、追い詰められると中邑さんは言います。そして、テクノロジーの進歩により、記憶することに昔ほど意味が無くなっていて、テクノロジーを使えば人が変わっていく時代に同じような人間を育てる必要は無い、と指摘します。
「デジタル機器に楽しさや自分の好きな事を見つけるのを頼りすぎていて、ずっと映像を見たり、ゲームをしたりという問題が起こっている。それが子どもの個性や好きな事を見つけるための壁になっていませんか」という森さんの質問には、中邑さんは「もっとリアルな経験が本当は必要だと思う」と答えました。
中邑さんはその実例として、この夏行った5日間のプログラムについて話しました。
中邑さんは、新千歳空港に中学生・高校生を集め、「森の馬小屋ってどこにあるか聞いてきて」という課題を出しました。普段携帯を使い慣れている子どもたちは、森の馬小屋がどこにあるかを人に聞くということが全くできなかったそうです。
子どもたちが1時間かかって集められなかった情報を、ネットで検索すればすぐに見つけられます。この落差を身をもって経験する事で、「実は、ネットの情報はタダで得られるものでは無いという実感を得ることから教育していこうと考えている」と、中邑さんは語ります。

次の日は子どもたちに6000円のお金で森の馬小屋まで行くことを課しました。しかも階段は10段以上使ってはいけない、という条件付きです。条件に合う行き方を探すと、20キロメートル離れた新得駅からタクシーに乗ることになりますが、お金が尽きるので途中で降りて歩かなければなりません。そうすると、スマホの地図を頼りに移動することに慣れている子どもたちは、途方に暮れます。
ようやく森の馬小屋に着くと、子どもたちはロープを1本渡されて、馬を捕まえてこいと言われます。けれども、簡単に馬は捕まりません。
こういう体験を通して、「僕たちは人間が本来持っている能力を発揮できないまま終わっていることに気付かせていく」と中邑さんは説明します。
DATA
登壇者名 中邑 賢龍 プロフィール 東京大学 先端科学技術研究センター 教授
香川大学助教授、米カンザス大学・ウィスコンシン大学客員研究員などを経て、2008年から現職。
テクノロジーで障害のある子どもたちの教育を支援する「魔法のプロジェクト」や異才発掘プロジェクト「ROCKET」などを立ち上げ、2021年6月より「ROCKET」を発展させた「LEARN」を開始。心理学・工学・教育学・リハビリテーション学だけでなく、デザインや芸術などの学際的・社会活動型アプローチによりバリアフリー社会の実現を目指している。登壇者名 長谷川 愛 プロフィール アーティスト。2012年英国Royal College of Art, Design Interactions にてMA(Master of Arts)修士取得。2014年から2016年秋までMIT Media Lab, Design Fiction Groupにて研究員、2016年MS(Master of Science)修士取得。2017年4月から2020年3月まで東京大学 特任研究員。2019年から早稲田大学非常勤講師。
2020年から自治医科大学と京都工芸繊維大学にて特任研究員。「Expand the Future(未来を拡張する)」というコンセプトのもと、アートやデザインを通じて日常の当たり前に問題提起を行う。作品が扱う社会的テーマは広範に渡るが、近年はバイオテクノロジーの進歩がもたらす未来の生殖や家族のあり方について問う作品を多く発表している。